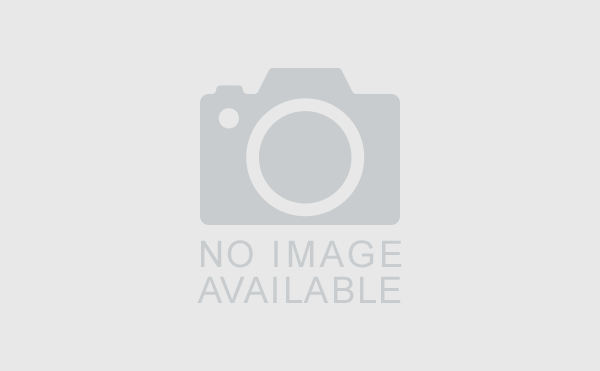徳川家が愛した【千鳥の香炉】
日本の美術工芸には、時代を超えて人々に大切にされてきた
“名物”と呼ばれる品々があります。
その一つが、今回ご紹介する【香炉 銘 「千鳥」】。
これは、かつて徳川将軍家に伝来した、
由緒正しき香炉です。
香炉とは、香を焚くための器となり、
主に香道で使用される香道具のひとつです。
【千鳥の香炉】の名を知ったとき、
私は思いました。
「なぜ“千鳥”?」
【千鳥の香炉】とは何か?
【千鳥の香炉】とは何か?
【千鳥の香炉】は、13世紀に中国・南宋から
元の時代にかけて作られた、龍泉窯製の青磁香炉です。
この時代の青磁は「砧青磁(きぬたせいじ)」と呼ばれ、
特に貴族や武家の間で高い人気を誇っていました。
名前の由来は、香炉の蓋に施された千鳥の意匠にあります。
千鳥は古来、吉祥の象徴とされ、「波に千鳥」の図柄は
「困難を乗り越える」「夫婦円満」などの意味を持ちます。
それが香道具に使われていたということは、
香の世界においても、「精神性」や「縁起」を
重んじていた証なのです。

歴史の中の【千鳥の香炉】
この香炉の面白さは、美しさだけではありません。
実はその来歴がとてもドラマチックです。
もともとは室町時代の茶人・武野紹鴎が
所有していたとされます。
彼の元から、豊臣秀吉、そして徳川家康へと渡り、
江戸幕府の誕生とともに、将軍家の重宝として
代々受け継がれていきました。
特に家康の没後には、「駿府御分物」として
尾張徳川家に下賜され、現在は徳川美術館に
収蔵されています。
この香炉は、いわば日本の政治と文化の中心を
渡り歩いた「歴史の目撃者」でもあるのです。

伝説を生んだ名品
さらに興味深いのが、
この香炉にまつわる石川五右衛門の伝説です。
ある夜、五右衛門が秀吉の寝所に忍び込んで
これを盗もうとした時、香炉の蓋にあしらわれた千鳥が
「チチ」と鳴き、五右衛門は捕まり、
三条河原で釜茹でにされてしまった
というエピソードが伝わっています。
真偽はさておき、これほどの香炉が人々の記憶に
「語られる存在」として残っていることが、
その価値の証明ではないでしょうか。

「名物」としての存在感
現在でも【千鳥の香炉】は、
名古屋の徳川美術館で大切に保管されており、
特別展などで展示されることがあります。
細部に宿る精緻な技巧、時代を超えた美意識、
そして歴史のロマン。
それらが香炉という小さな器の中に凝縮されているのです。

最後に
現代では、香道具と聞くと少し遠い存在に
感じられるかもしれません。
でも、【千鳥の香炉】のような名品には、
ただの道具ではない物語と精神性が詰まっています。
それはまるで、時代を超えて静かに語りかけてくる
「香りの声」。
もし機会があれば、ぜひこの香炉の前に立って
その歴史と美に触れてみてください。
きっと、心のどこかで「千鳥のさえずり」が
聞こえてくるはずです。